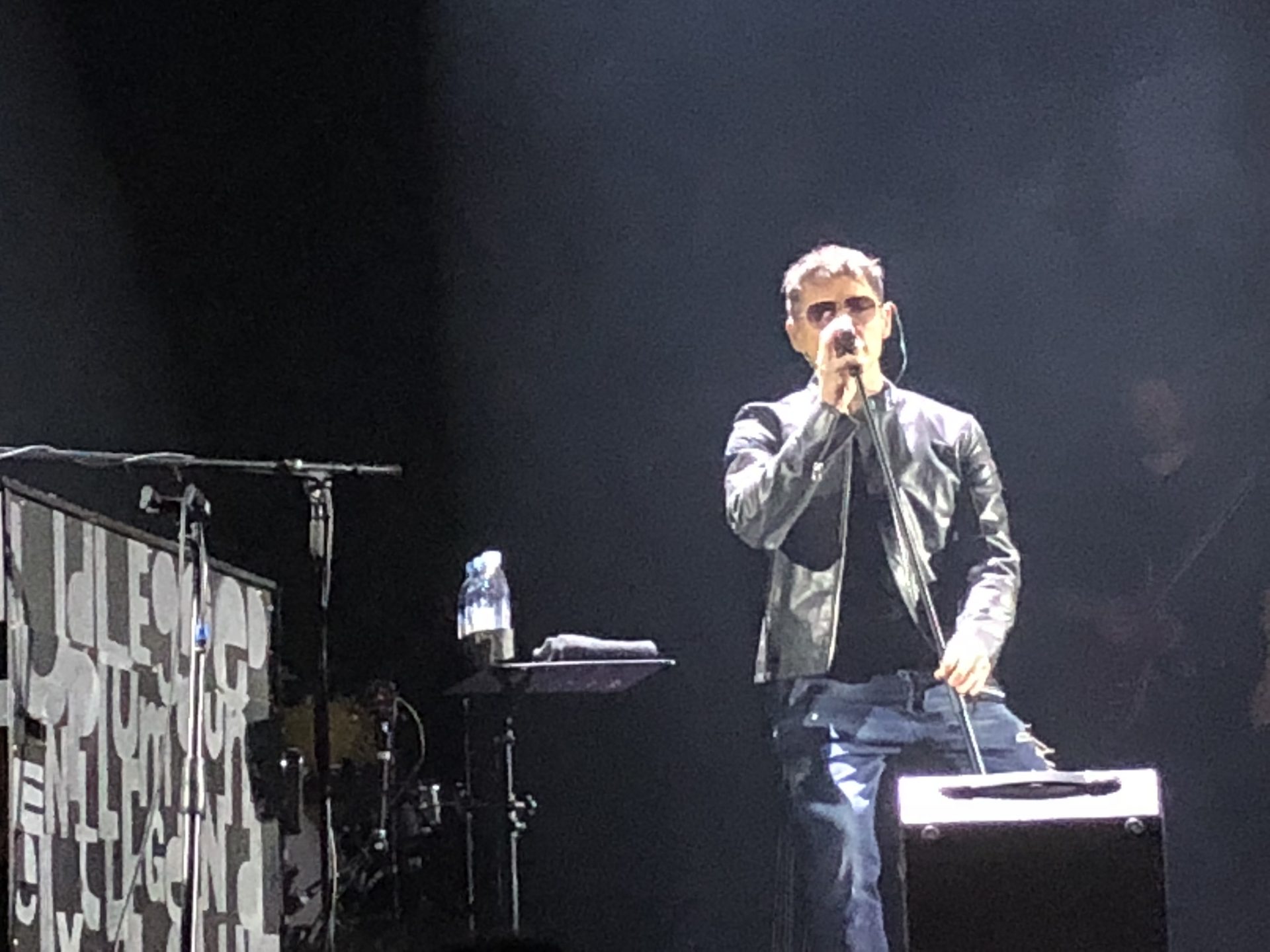『Hjemkomst Morten Harket 1993-1998』読んでいます。昨年、Håvard Rem氏が来日したとき、「ポールの伝記本の著者がモートンの本を書いていて、いろんな人にインタビューしている」とは聞いていたんですが、既に最初の10ページで、『Wild Seed』とは別の、当初の予定だったソロアルバムについて、結構な情報量です。ページめくる度に、「そうだったのか」だらけです。この項、要するにネタバレなので、ネタバレしたくない人はブラウザバックでお願いします。
1993年~1998年当時のこと(notネタバレ)
1993年~1998年といえば、マグネのいう「僕ら90年代は殆ど活動してないから」という時期。実は、自分がネットを始めたのもちょうどこの時期だったんですが、Netscapeが1994年にリリースされて、「ホームページ」というのが、広がっていった時期でもあり、モートンの公式ホームページも、『Wild Seed』のリリースと共に公開されていました。(今のサイトとは別)。(日本の場合は96年くらいまでが、企業と理系大学の学生中心、その頃から少しずつ主婦層などにも「個人ホームページ」が増えていった感じ。)
モートンサイトのトップページはうろ覚えですが、アルバムのジャケットと同じだった記憶です。1996年くらいから、a-haとしての活動は1993年の「Memorial Beach」以来、1998年の「ノーベル平和賞コンサート」まで停止します。
以下、ネタバレベースですが、本の翻訳ではなく、これまでの自分のブログからの引用なども含みます。
『Wild Seed』ではないアルバムは、Alan Tarneyプロデュースだった
Warnerは、a-haと契約したときに「ソロの時もワーナーで出す」という契約を結んだそうで、その第一弾として企画されたのがモートンのソロ。「マグスやポールでは難しい」という判断だったとのこと(何が難しいかは謎)。ま、何はともあれ『Take On Me』をヒットさせたAlan と、当時、超アイドル的人気のあったバンドのボーカリストを組み合わせたことは間違いないですね。個人的な感想ですが、ありがちな、”アイドルグループの人気を利用してソロで一発あてる”的な匂いを感じます。
本によると、このソロプロジェクトでは、Prefab Sproutのメンバーに曲を提供したこともあるRobert Carrや、今は映画音楽で活躍しているAlanの息子Oliver,そしてモートンとのデュエット相手としてAlanの娘も参加していたそうです。ちなみに、そのデュエット曲は、Crying in the rain同様、Everly Brothersの “Devoted to You” 。モートンが、やりたいと希望したのだそうです。
実現してたら、綺麗な曲になったのは想像に難くないですね。実際に、モートンバージョンを聞いた著者は「オリジナルより長く、でも内に流れているものには、若干ではあるけど同じ物を感じた。美しく綺麗だった。間違いなくハルケット(という感じ)だった」と言っています。
同じアルバムに入っている曲で、なぜか流出しているのはこれ。
うん、まさに「間違いなくヒットしそうな、アランプロジェクト」ですね。しかし、ご存知の通り、「Wild Seed」にAlan Tarneyの要素はありません。ここで思い出すのが、先日のLindmoでのRock In Rioで大観衆を前にして、モートンが感じたことについての発言です
Morten:僕らにとっては「いつも通りのお仕事」だったのさ。僕らはそこで、僕たち自身だっただけ(笑)
ああ、いや、そういうことを言いたかったんじゃないんだ(笑)
でも、それは僕が抱えていたことでもある。
その状況下で僕は自問自答したんだ、
「OK,これは僕にとっての転換期だ、そしてこれは続いていって、数ある転換期の一つになるだろう」って。
「君はどうしたいの」って僕は自分に問いかけるんだ。 「何をもってどうしたいの」って。
自分に向き合って、何をどうしたいか、若干の「力業」を使って自分に必要なものに向き合い、それ相応の覚悟をもって臨んだソロプロジェクト。しかし、蓋をあけてみれば、ここまでAlan Tarney色が強いという。ただの1ファンである自分ですら、88年くらいからのモートンの発言には、「自分で曲を作りたい」というのを言葉の端々に感じていたほどでした。お仕着せの、モートンが歌ってさえいればよさげなアルバムが、当時のモートンの気に入らないであろうことは、本を読む前から想像できます。ポールとマグスの代わりに他の人が書くだけのアルバムが果たして、本意であろうはずがありません(断言)
モートンの思い、Alanたちの思い
モートンの思い
僕は、水中深くまで身を投じるつもりだった。でも、そうではなく、何もかもがTarneyのいる沿岸で起きていた。次々と明確な形になっていって、僕は「待った」をかけられなかった。僕は自分で曲を作りたかったのに、その時点でまだ出来ていなかった。僕は急いで、曲作りを作るための、自分を押し込んで集中できる場所を探さなくてはならなかった。それがいつ終わるかも、誰かとの共同プロジェクトになるのか、自分で曲作りするための場所をみつけられないまま終わるかもわからなかったけど。Tarneyのプロジェクトを盗んで自分のものにしようと思ったわけじゃないけど、次第に曲が明らかになってくると、二つのプロジェクトになった。ソロアルバムのプロジェクトを開始し、ワーナーとサインを交わしたとき、僕は、分かれ道に来ているとわかったんだ。アーティストとして進むか、それとも全く違うことをするのかの。
結果的に、モートンはこの二つのアルバムの両方をワーナーに聞かせて、判断はワーナーに仰いだ結果、採用されたのが、モートンにとって「二つ目の」プロジェクト…。自分で曲を書くことに拘ったほう…つまり『Wild Seed』になったようです。
僕は、レコーディングに全身全霊をかけなければならなかった。そうでないと、誠実とは言えないから。だから、自分の胸で(*1)別のアルバムを作らなくてはならなかった。(この項、2019/11/1に修正しました)
結果として、レコード会社も選んでくれる良い物となった。僕はどっちを取るかについては、一言も言わなかった。僕は二つとも提出したんだ。その二枚目こそが『Wild Seed』だった
僕は正しいことをしたと思ってる。Tarney盤は良い曲もあったけど、でも、僕は娯楽歌手じゃない。それは過多ではなかったけど、根本のところで失敗があったんだ。こうもいえる。正しいことをするときは、乗り越えるべきことがあるって。勿論、全く違うこともできたと思う。やりたくないって言うとか、自分の素材だけでやるとか。僕はa-haのモートンだったから、ソロアルバムを出すのであれば、それは特長のある、その人じゃなきゃできないものである必要があったんだ。ただの良いアルバムではなくてね。
(*1)自分の胸で…というのは、ノルウェー語の「自力で(=自分の手で)」の言い回しをモートン流に替えたものだと思います。前後の文脈を読む限り、自分の力で心のこもったものを・自分の心で決めたものを…というのを含んでいるように思います。(2019/11/1追記)
モートンのソロ活動は、当時、メンバーも知らなかったらしいので、『Wild Seed』は内緒のソロプロジェクトの更に奥地でひっそり収録されたということですね。このアルバムを購入して、聞いた時の気持ちは今でもハッキリ思い出せます。「ついにやった」と。前にもどこかに書いた覚えがありますが、87-88年頃のインタビューでは、本当に年がら年中「ポールやマグスは曲を作るのに、あなたは歌ってるだけなの」という不躾な質問をされていることが多く、同じように、他のバンドのファンのクラスメイトからも「ねえ、モートンって声と顔だけ?」と聞かれてウンザリしていたのです。だから、『Wild Seed』が出た時は、もうそのクラスメイトはいなかった(高校卒業し大学も卒業して就職してた)けど、誰に言うわけでもなく「ほらみろ!」と思ったのでした。やっとあのウンザリする質問から離れられる(聞かれるのも読むのも)と。
Alanたちの思い
Alan はソロアルバムの契機と、このアルバムがリリースされていたらどうなっていたかについて、本の中で答えています。
レコード会社が何をしたいか、はっきりしなかった。それはモートンも同じ。でも、レコード会社が電話してきたので、何かやらねばならないことはわかった。僕はこのアルバムの曲を、Robert Carrと一緒に曲を作ってくれた息子Oliverと同じように感じていた。彼らの書いた曲にモートンの声はぴったりだと思った。だから試したんだ。同時に他の二人がいないa-haのアルバムのように聞こえてはいかなかったから、難しかったよ。
モートンは情熱的だった。僕たちのすることを好んでくれていた。僕は、モートンが録音したテープをすり切れてしまったから新しいのがあるかと聞いてきたのを覚えてる。彼は繰り返し聞いてくれていたんだ。
(このアルバムが出ていたらどうなっていたかの質問に)
そうなっていたら、最善の方向には成らなかったかもしれない、世界中では売れなかったかも。でも良いアルバムになったのは確かだ。僕にとってもね。きっと素敵なアルバムにはなっただろう。まだ途中だったから…。(註:このもう一つのアルバムは完成してない)
僕がこの時考えていたよりも、モートンにとっては難しいことだったろうと思う。彼は、ただの1歌手ではなくて、他の曲も歌う人になりたかったんだ。そして、まさにそうなるための道だったんだ
Robert Carrと、Oliverはそれぞれメールで、こう答えています。
とっても残念だった。プロジェクトはもう終わりに近づいていたし、もっとも残念だったのは、このプロジェクトは若い人にとって、未来を開いてくれるものだったから。(Robert)
残念だった。でも、もう今は昔のことだから。今は殆ど考えないよ。僕が覚えているのは、『Wild Seed』を聞いたとき、その素材の中の闇に驚いたことなんだ。後になってみれば、これこそがモートンが進むべきキャリアだったのは明らかだ。(oliver)
レコード会社に渡すデモテープが出来るまでにプロジェクトが進んでいたわけですから、残念なのは当然といえば当然ですが、この彼らの思いと温度差を見る限り、また、流出している2曲をあわせて聴く限り、曲も良いし、リリースされたらキャッチーで、「モートンマジ王子」的なアルバムになった気がしますが、同時に、意外性があまりないという意味で、スペルマンアワードを独占するようなアルバムにはならなかったかもしれないとも思います。
今になってみると、アルバムのタイトルが『Wild Seed』なのは、作詞も作曲も一人でやったのがこの曲だからかなとか、色々思うところはありますが(そして本を読み終えてない以上、あとでその理由も出てくるのかもしれませんが)、まさにモートン自身が、自分のキャリアを花開くために作ったアルバムとも言えるかもしれません。
それにしても、もう一つのアルバムがいくら「お仕着せ」だったとはいえ、『Wild Seed』作成時にはRemさんとモートンはあちこち旅に出ながら作詞したという話ですし、どうやって時間作ったんだろう感満載です。1993年にソロプロジェクトが開始したといっても、『Poetenes Evangelium』もありましたしね。常々、「マグスに時間管理講座やってほしい」と言っている自分ですが、モートンにも聞いてみたい気がしてきました。